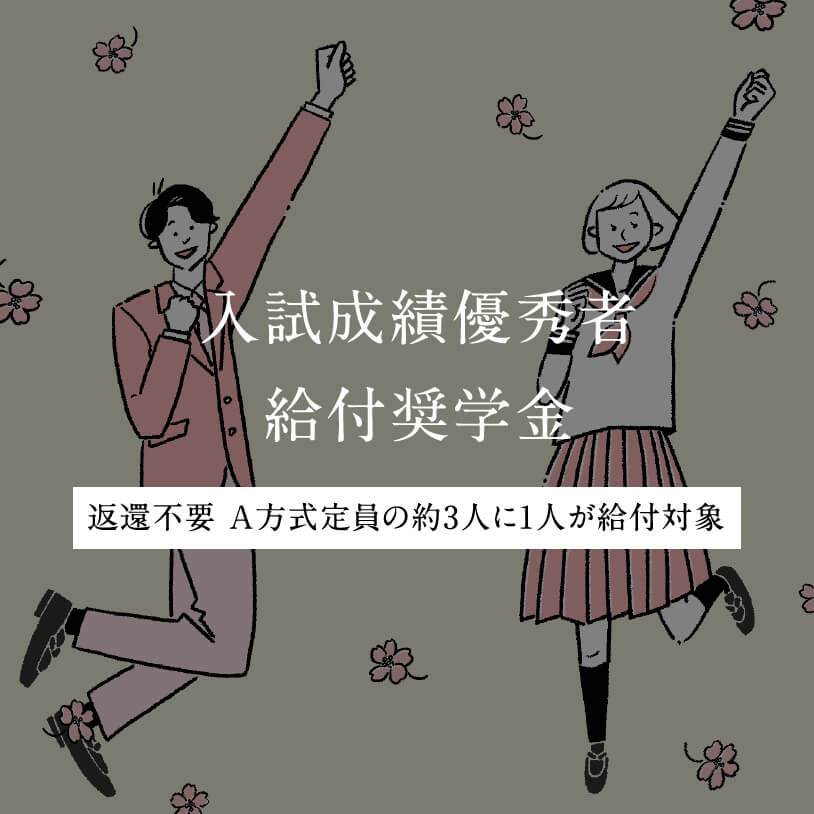履修の流れ
-
1年次
社会福祉学の思想・哲学・価値が、一人ひとりの「いのちと暮らし」を大切にし、経済活動や法制度、市民活動などの社会の骨格となっていることを理解する。
-
2年次
児童、高齢者、障害者などの領域に関する知識を修得し、ボランティア実習・演習による体験的な学びを通じて社会福祉学の基礎的な知識、実践方法を身につける。
-
3年次
1・2年次の学びを福祉現場で実習として体験し、理論と実践の融合を図る。卒業後の進路を見定め、福祉系専門職※としての知識と技術を修得する。
※国家資格である「社会福祉士」にも対応。 -
4年次
1年次~3 年次で学んだ知識と多彩な体験を活かして更に深い学びを行いながら研究のまとめを行い、卒業論文を仕上げる。専門職としての知識と技術を修得し、「社会福祉士」を目指す。
社会を読み解く
幅広い学び
社会福祉分野の課題解決のために、社会学や心理学、文化人類学など、幅広い領域の学びを取り入れ、あらゆる人の命を守り、共に豊かな人生を生きることができる社会の構築に挑戦します。介護や保育、災害支援など多様なフィールドでの実体験を通して、社会を読み解く分析力、解決の方法を見出す企画開発力、課題解決に向けた実行力を養います。
地域連携活動への参画
多彩なゼミ活動をベースに、地域と連携したさまざまな福祉関連プロジェクトやボランティア活動に参画することができます。援助を必要としている人たちとの対話や、支援活動を行うさまざまな人びととの交流を通じて、自分にできること、すべきことを発見していきます。
- 活動例
- サイクル・プロジェクト/ほっかほっかプロジェクト
3つの科目群と
実習・演習
フィールドワークを重視し、
理論と実践を融合
「福祉の思想・哲学・価値」の理解と、「科学的な知識・思考」と「技術・援助方法」を獲得し、フィールドワークに参加。支援を必要とする人達を理解し行動するチームワークを身につけます。
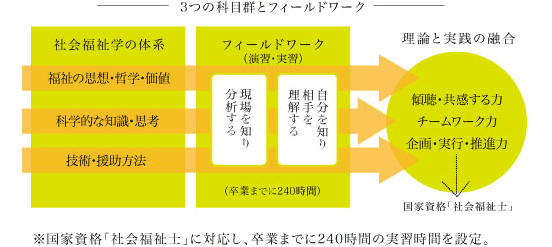
国家資格「社会福祉士」への対応
「社会福祉士※」の受験資格を得るために必要な科目を開講。資格試験対策としての全体指導、個別指導、模擬試験等を実施すると共に、個別学習カウンセリングを実施。
2022年度 国家資格「社会福祉士」24名合格
過去5年間(2018~2022年度)で 120名合格 ※既卒者含む
※社会福祉士とは、公的機関(福祉事務所、児童相談所など)における相談援助業務を行うケースワーカー、社会福祉協議会やNPO団体などにおける地域生活支援活動を行うコミュニティソーシャルワーカー、福祉施設における相談員・指導員・支援員、一般病院などの医療機関における相談援助などを行う医療ソーシャルワーカー、地域包括支援センターにおける介護相談・支援、ハローワークなどを中心とする就労相談支援などの相談援助を行う専門職の基礎的資格です。
卒業研究テーマ例

- ●里親委託の推進と里親支援の充実にむけて
- ●過疎の解消に向けて若者のU・Iターンを促進するための住みたいまちづくりに関する研究
- ●知的障害者と選挙制度についての考察―知的障害者における意思決定支援の有り方
- ●てんかん患者の就労実現にむけて
- ●介護人材の確保・定着に向けての社会的方策に関する研究
- ●介護ロボットの活用―介護不足を減少させることはできる
- ●岐阜市の駅及びバスに関するバリアフリーに関する考察
- ●女性労働の現状と課題―女性が働き続けられる社会への転換
研究紹介

中田雅美 准教授
専門分野/社会福祉学、地域福祉研究
一人ひとりのLIFE、普段の暮らしの
幸せから地域社会を考える。
福社はふだんのくらしのしあわせ(ふくし)と表されることがあります。そして人は必ずどこかで暮らしています。どこかとは、自宅や施設などと捉えることもできますし、国や地域、社会と考えることもできます。研究の関心は、「誰もが自分のLIFE(生命・生活・人生)を生き抜くことができる社会とは どのようなものか」、「そうした社会をいかにつくっていくのか」です。現在は過疎地域で暮らす方が住み慣れた地域で、最期まで暮らし続けられる方策を考えたいと、踏査や調査研究に取り組んでいます。また、韓国やデンマークにおける社会福祉・ソーシャルワークの比較研究にも取り組んでいます。