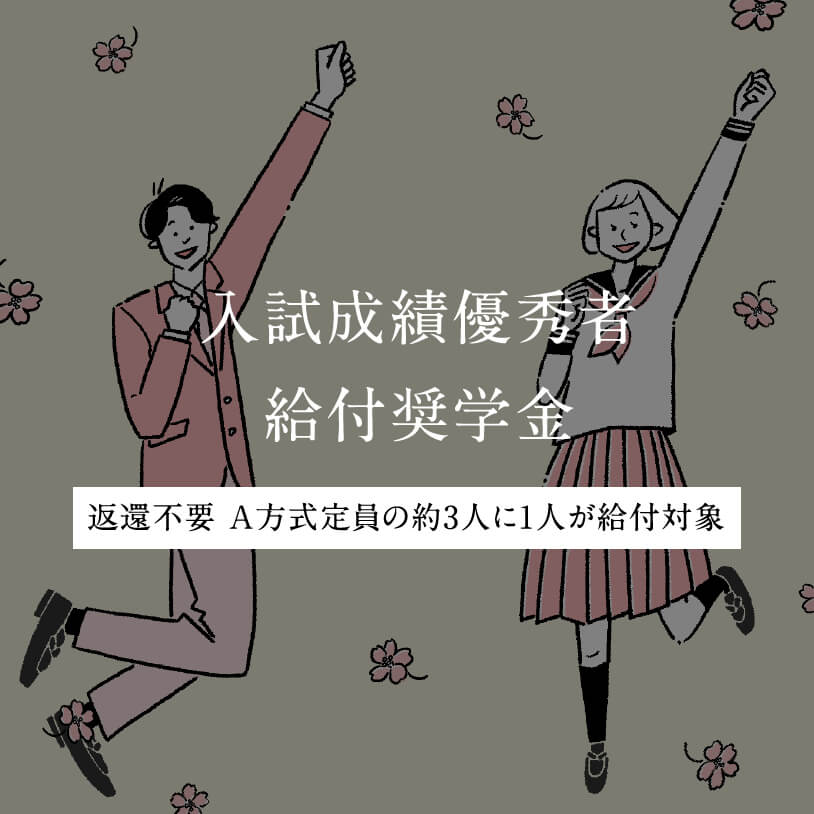履修の流れ
-
1年次
グローバルな動向とローカルな現象との関係に着目し、異文化交流・多文化共生についての基礎知識を学ぶ。
-
2年次
英語を学びながら、異文化体験や交流を通じて文化人類学を学び、海外フィールドワークの技術を身に付け、実践(必修)。カナダ・オーストラリア・マレーシアから選択。
-
3年次
海外の研究者・博物館学芸員による講義、博物館でのショート・インターンシップを体験し、修得した知識と技術を実践する。※
研修先:タイ・イタリア・トルコ・南アフリカ・インド等
※選抜制 -
4年次
1年次~3年次で学んだ知識と技術と多彩な体験を活かして、更に深く学びながら研究のまとめを行い、卒業論文を仕上げる。
文化人類学をベースに
世界を理解する
文化人類学は、現代社会を文化の営みから捉え、人間とは何かを考える学問です。国際文化専攻では、グローバルな動向とローカルな現象との関係に着目し、異文化交流・多文化共生によってつくられる新たなつながりを文化人類学の視点から考え、理解から実践へと結びつけています。
博物館学を核に
情報発信力を磨く
文化人類学と博物館学※をリンクさせながら、「もの」の先にある人々の暮らしや文化を、フィールドワークを通じて理解していきます。また、フィールドワークで得た経験や資料を他者にわかりやすく伝えるエスノグラフィーとプレゼンテーション手法を学ぶことで、社会における高度なコミュニケーション力を獲得していきます。
※博物館における資料の収集・保管・展示および調査研究等に関する科目を設置し、国家資格「学芸員」資格取得にも対応。
海外フィールドワークの
実践
海外でのフィールドワークを通して、異文化理解に欠かせない豊かなコミュニケーション能力を身につけるための科目を充実。
- ●TOEIC®テストスコア600点以上で2単位、730点以上でさらに2単位修得できる。
- ●海外留学による単位認定を多く設定、休学しないで長期留学し、4年間での卒業も可能。
海外短期研修/
専攻内学生全員参加〈必修〉
| 期間 | 2年次 夏季休暇(約2週間) |
|---|---|
| 研修先 | オーストラリア、マレーシアから選択 |
| 内容 | 英語の学びと共に、異文化体験や交流を通して、フィールドワークや文化人類学研究の基礎を学ぶ。 |
※期間、行先、内容は変更となる可能性があります。
海外短期研修の目的
グローバル化する世界の動向とローカルな現象から、国境を超えた新たなつながりを創造する人材の育成を目指します。
海外短期研修 参加者の声

マレーシアで海外短期研修に参加
12日間の滞在から学んだ
異文化に対する意識。
クアラルンプール
今まで学んできた文化人類学の知識の活用や、フィールドワークの実践、語学力の向上を目的に、3月上旬の12日間、マレーシアで海外短期研修を行いました。はじめの8日間は、首都クアラルンプールにあるAPU(Asian Pacific University of Technology & Innovation)に滞在し、英語の勉強をしました。この大学は成績別にクラスが分けられており、私はレベル3の標準クラスでした。しかし、授業は全て英語で行われ、日本をはじめロシアや中国などさまざまな国の留学生がとても積極的に授業を受けていることに圧倒され、常に授業は置いてけぼり状態でした。四苦八苦しながら同じクラスになった国際文化の友達と協力して課題や発表を乗り越えました。授業後のクアラルンプールでのフィールドワークは、自分達で行き先を決めてタクシーで観光地を回ったり、買い物をしたりと、海外に行ったことのなかった私は毎日が新しい発見ばかりでとても興味深かったです。

テメロー
クアラルンプールでの語学研修が終わったあと、テメローという村で二人組になって2泊3日のファームステイをしました。私がお世話になったステイ先は、ホストファザーもホストマザーもほとんど英語が話せず、3人の子どもとも日本語とマレー語で会話するという状況でした。しかし、会話するときは笑顔を意識したり、ジェスチャーで表現したり、スマホの翻訳機能を駆使することでなんとかコミュニケーションをとることができました。私のステイ先は、環境面では裸足で和式のトイレに入ったり、桶に溜まった水で体を洗ったりと、他の国際文化の人のステイ先よりも環境が整っていない家で、普段の日本での生活からは考えられないことが多くありました。しかし、ここは日本ではなく違った文化が形成されているため、「自文化を中心に考えてはならない」ということを意識すると、自然とすべてのことを受け入れることができました。滞在2日目は、テメローの学校に行き日本文化の紹介と異文化交流を行いました。そこで仲良くなった学生とはSNSで交流を続けています。

海外短期研修を終えて
マレーシアでの海外短期研修を通じて、英語が母語ではないマレーシアの人たちと会話するときは文法を気にしなくてもいい反面、自分も相手も曖昧な英語しか話せない状態だと、意思の疎通が難しいことがわかり、今後の英語を勉強するモチベーションにつながりました。異文化交流に関しては、ムスリムの女性が身につけるヒジャブを被ったり、手で食事をしたり、言葉が通じない人とコミュニケーションをとったりと、いろいろな経験ができました。なによりこの12日間で一番印象に残ったことは、異文化での生活にすぐ順応することができる新しい自分を発見したことです。異文化があることで初めて認識できる自分もあるのだと感じることができました。この海外短期研修の経験をこれからの大学生活でも活かしていきたいです。
現代社会学科 国際文化専攻(愛知県立豊丘高等学校出身)伊藤 有彩
2020年5月の取材内容です。現在の研修期間は2年次の夏季休暇になります。
※内容は変更となる場合があります。
海外博物館研修/専攻内選抜制
| 期 間: | 3年次夏季休暇(約2週間) |
|---|---|
| 研修先: | 候補:タイ、イタリア、トルコ、南アフリカ等 |
| 内 容: | 海外の研究者・博物館学芸員による講義、博物館でのショート・インターンシップを体験。 |
海外博物館研修/専攻内選抜制

イタリアで海外博物館研修に参加
イタリアの文化を肌で感じ、
広い視野と確かな知識を
獲得した2週間
美術館や博物館にて貴重な展示資料を鑑賞
研修では、ウフィツィ美術館やポンペイ遺跡をはじめとして多くの博物館、教会や遺跡に足を運びました。どの博物館にもボッティチェッリやダンテの作品など、多くの貴重な資料が展示されていました。出発前に『博物館実習』の授業で日本の博物館は、空間ごと美しく魅せることや、教育機関での使用が多いことを考慮した講座を開いていることなどに特徴があると学びました。しかしイタリアでは廊下にまで作品が並べてあり、価値のあるものをとにかく多く見せることが特徴的でした。更に文字が読めない民衆がいた時代に、絵によって布教していた文化がそのまま建物に残されているなど、時代を感じられる文化財が多くありました。


現地だからこそ知った文化財の価値
遺跡や博物館では、国際文化専攻の教授やガイドの方から丁寧な解説をしていただき、自分達だけでは気づかなかっただろうポイントにたくさん目を向けることができました。例えばかつて西洋の建築は高さで権力が表されていましたが、後に横幅の長さや面積で権力が計られるようになったため、宮殿は横に長い構造が多いと学んだことが大変印象に残っています。また亀井先生の研究しているアルベロベッロという地域には今でも人が暮らしている「生きた建築文化財」があります。屋根には魔除けのために独特な模様が描かれていたことなどから、建築文化財と共に、その土地ならではの文化や歴史、宗教観を感じることができました。更にアルベロベッロの建築で、私は2階にあった穴について疑問を持ったので、博物館のスタッフに聞いたところ、もともと小麦を保存するためだったということがわかり、当時の住民の様子を感じることができました。このように知識を身につけた上、さまざまな疑問を持つことによって、より深く物事を知ることができると実感しました。また1年次の『博物館概論』というユネスコ世界遺産と博物館に関する授業で、アルベロベッロの建築を学んでいたため、実際に現地を訪れたことで学びと体験がつながる瞬間を味わうことができました。

海外博物館研修を終えて
この経験を通して確かな知識、広い視野、新しい考えが身につき、少ない人数だからこそガイドの方や教授と接する機会が増え、とても充実した研修になりました。今後は、臆することなくさまざまな地に足を運び、多様な角度から興味を持つことを大切にしながら、学びを深めていきたいです。
現代社会学科 国際文化専攻(愛知県立瑞陵高等学校出身)山口 亜希子
2020年5月の取材内容です。期間、行先、内容は変更になる可能性があります。
卒業研究テーマ例

- ●民族スポーツから国際スポーツへ~日本の船競漕とドラゴンボートレースから~
- ●日本文化における異文化の受容とその発展―西洋の『魔女』の描かれ方―
- ●保存鉄道―文化遺産としての鉄道―
- ●絶えないイレズミについての考察
- ●国際協力の36年:あるNGOの英文ニュースレターを通して
- ●大学生のまちづくり:多文化共生を目指して
- ●日本におけるフェアトレード運動
- ●フィールドワークを通してみた外国籍児童の教育
- ●想像し、創造される伝統―浦添市勢理客獅子舞の姿
- ●よそ者としての環境保全団体から見る“地元”と“よそ者”の関わり―百名山・伊吹山における保全活動のエスノグラフィー
- ●なぜチアリーディングは日本で広まらないのか
- ●占い師の戦略:占いの館でのフィールドワークから
研究紹介

岡部真由美 准教授
専攻分野/文化人類学、上座部仏教研究
現代世界における宗教の
よりよい理解を目指して。
1980年代以降、急速な経済発展を経験した東南アジアのタイでは、布施(与える、施す)という上座部仏教の主要な修行をつうじて、人びとが働いて手にするカネが大量にお寺に集まるようになりました。「仏教ビジネス」への批判も強まるなか、布施をどのように獲得・使用すべきかをめぐる規範は揺れ動き、お寺や社会がどうあるべきかが問い直されています。この変化の過程をフィールドワークで明らかにすると共に、グローバル化に併って増加する他の非営利組織(NGO/NPO等)との類似点や相違点を探ることによって、現代世界における宗教のよりよい理解を目指しています。